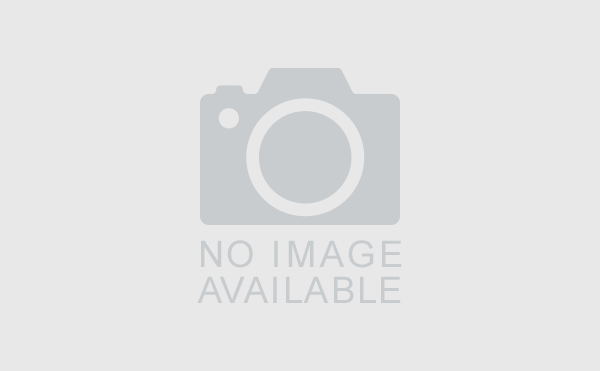「休日」は意外と難しい…その1 「法定休日」、「週休2日制と法定休日」について
労基法の休日(法定休日)の規定は、以下のとおり簡潔です。しかし、規定が簡潔だからといって、留意すべき点が少ないわけではありません。以下では、「その1」として、時折お問い合わせいただく労基法第35条「休日」について、原則の週休1日制と週休2日制の関係、労基法の規定(第37条)の休日割増又は時間外割増が交差する場合について確認します。週休1日制の例外である変形休日制や休日振替については、稿を改めて、「その2」で確認します。
第35条
1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
【第35条第1項:毎週少なくとも1回の休日について】
第1項は、週1休の原則の規定です。ここでは、まず、原則のご説明と、その原則のもとでの応用問題(週休二日制との関係)をご説明します。
〇「週」とは
・35条は、「週」について特定しておらず、「歴週」つまり「日曜から土曜」であるとは限りません。就業規則等で例えば「土曜から日曜」などと定められていれば、それによることになります。就業規則等に特段の定めがない場合は、「週」は、「歴週」つまり「日曜から土曜」であるとされています。これらの考え方は、労基法32条の「1週間」についての解釈と同様です(昭63.1.1基発第1号)。
〇「暦日休日制」の原則
・「休日」(労働義務のない日)とは、暦日すなわち0時から24時か単に連続した24時間のいずれかについては、厚生労働省は「原則として暦日休日制」としています(昭和23.4.5基発535号)。この原則によると、8時から翌日の8時までの24時間勤務を繰り返す1昼夜交替勤務の場合、勤務終了から次の勤務開始までの24時間は休日とは認められず、いずれかの勤務終了日に続いて1暦日の休日を設けないと週休1日を確保することができないことになります。なお、「暦日休日制」の例外としての連続24時間制休日は、化学工場のように8時間三交替制が取られる場合の二番方と、旅館業で、客のチェックイン時間から翌日のチェックアウト時間までの2暦日にまたがる勤務について、一定の条件を満たす場合に限り認められています。
〇「休日」の特定
・労基法35条は、「休日」が週のいずれの曜日かを特定しておらず、歴週または就業規則所定の週のうちで1日の休日があれば適法となります。その結果として、2週間のうちの最初の日曜と次週の週末土曜を休日とする12連続勤務も可能ということになりますが、このような例は、労働者の生活リズムや健康管理の観点からは望ましいとはいえません。厚生労働省は、「労働者保護の観点から、休日の特定が望ましい」(「平成22年版労働基準法」466頁)としており、行政指導においても休日を特定するよう指導するとしています(昭63.1.1基発第1号)。
・法定休日に限らず法定外休日についても、労働者の生活リズムを安定させるなどの理由で、就業規則等で休日を特定すること、また、例えば「日曜日を法定休日とする」のように法定休日を定めることは、労基法37条との関係も含め望ましいことはいうまでもありません。ただし、シフト制のように曜日を特定しずらい場合は、「週2日、勤務割表による」などとし、法定休日を特定しなくとも、後述する「週休2日制と法定休日」で説明する解釈により、労基法上は適法となります。
・なお、国民の祝日に関する法律が定める「祝日」は、国民に休むことを義務づけるものではなく、また、労基法35条の休日の規定を規制するものではありません。したがって、祝日に労働させても労基法違反とはなりません(昭41.7.14基発739号)。
【週休2日制と法定休日】
〇労基法37条の休日労働と週休2日制-法定休日が特定されていない場合
「何らかの週休2日制」(完全週休2日制のほか隔週週休2日制などの計)は、企業規模を問わず80%以上の企業が導入しています(厚労省「就労条件総合調査」2022年)。就業規則等で法定休日が特定されていない場合、2日の休日のいずれが法定休日(労基法37条の休日労働割増の対象)になるかという問題があります。ここでは、一例として、日曜と土曜の2日が休日という例で考えます。
・まず、日曜と土曜のいずれの日にも働いた場合はどうでしょうか。「歴週」の場合は後順の土曜が「法定休日」、就業規則で「週」を例えば「月曜日から日曜」としているときは、後順の日曜日が法定休日になるとされています(厚労省平21.10.5「改正労働基準法に係る質疑応答」)。
・次に、日曜または土曜のいずれか1日、働いた場合はどうでしょうか。厚生労働省の前掲書は「完全週休二日制をとる場合には、週2回の休日のうちいずれかの日に労働させたとしても、他の1日の休日が確保されている限り本条違反にはならない」、つまり、法定休日を特定しなくてよいとしています。37条の休日割増との関係では、働いた1日についてはその対象にはならないということです。隔週2休制など完全週休2日でない場合も、休日2日の週であることが就業規則等で特定されていれば(例えば、「休日は以下のとおり。1.日曜日、2.○○○○年〇月〇日を起算日とする2週間ごとの土曜日」)、法定休日を特定する必要はないと考えます。これについての根拠は、以下であらためて触れます。なお、休日のうちの1日を働いた結果、週40時間超になった場合は、休日労働ではなく時間外労働として2割5分増以上の割増の対象となることはいうまでもありません。
〇週休2日制において法定休日を特定しなくてよいとする理由
・安西弁護士は「労働時間・休日・休暇のための法律実務」(2006年)385頁~386頁で、次のように述べています。
・「たとえば、土・日曜の2日とも「休日」と定めておけば、それは選択債権となり付与義務のある使用者の選択によっていずれかが法定休日として指定されて定まる(民法406条)」。この規定によれば、「使用者において、週2日の休日のうちの1日について労働させた場合には、結局その日を休日とすることは法的に不能になるから。他の1日が自動的に法定の休日として特定されることになる(民法旧410条の履行不能による選択債権の特定)」ので、法定休日と法定外休日との区別は「就業規則上においてする必要はなく、両日とも単に「休日」とのみしておけば足りる」としています。選択債権である法定休日をあらかじめ特定しないほうが、休日労働割増(×1.35以上)の負担を回避することができるという解釈です。なお、民法410条の改正後についての私見は(※)に注記しました。
・この解釈は争う余地はないと思いますが、隔週週休2日等を含む何らかの週休2日制の普及率が中小企業でも80%を超えている状況を考えると、休日労働割増がないことについての労働者の不信感や、法定休日が特定され休日労働割増の支給基準が明確な企業の労働者と比べた場合の不公平感が生じうることに留意する必要はあります。法解釈とは別に、企業内の個別労使関係の安定等の観点に立てば、法定休日を特定することは推奨されてよいのではないかと考えます。
※民法410条の改正について
上の第1文の「また」以降については、民法410条の改正により、選択権を有する者(原則として債務者=使用者)の過失によって不能になった場合、残存する債権(休日)に特定されるけれど、それ以外の場合は、広く不能の債権(ここでは、日曜または土曜のうち労働日となった日)も選択できることになった解されます。要は、債権について選択権を持っている人(使用者)は、過失がなければ、不能の債権(休日)を選択することもできると言っているわけですが、週2日の休日に関して言えば、使用者が、不能となった債権=休日を法定休日として選択するとは考え難いので、安西弁護士の後段の記述は、現在も有効ではないかというのが私見です。
民法406条(選択債権における選択権の帰属)
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは,その 選択権は,債務者に属する。
民法旧410条
1 債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
2 選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。
民法現410条 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
改正に関する解説 https://www.yokohama-roadlaw.com/column/60_410.html